「独り言」」:NHKドラマ10「舟を編む」の再放送が終わりました。
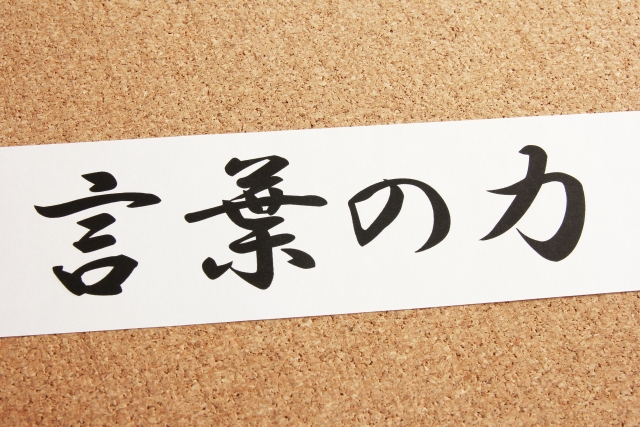
2025/8/19 NHKドラマ10で再放送されていた「舟を編む」が終わりました。
初回も再放送も見ました。
映画も観て、原作までも読みました。
映画は、原作に結構忠実な印象がありましたが、映画とテレビでは、脚本も違うし、当然描いている部分も違います。
その違いは違いとしてですが、やはり映画の見せ方と、テレビドラマ(複数回で完結)の見せ方って結構違う印象でした。
特にテレビドラマを見て、話しそのもものだけでなく、「ことば」の多様性に改めて、興味が湧いてきます。
このドラマの再放送中に、NHK Eテレで「チ。~地球の運動について~」という番組も再放送中なのです。
このドラマは、中世のヨーロッパの天動説主流の時代に、地動説が異端として迫害されていたころの話をベースに、展開されるアニメです。
この中でも、「文字とかことば」の話がでてきます。
その中で、私が印象に残っているのは、「文字は、時空をこえた人とも対話できる」そんなことや、「活版印刷」が大量に情報を広げることに有効で、それこそが、人々が自分で考えるきっかけにつながり、それこそが自由の出発点であるような話があったように思います。
文字で書かれた文章の意味が伝わらなければ、書いた人の気持ちはつわたりません。
そのために、「辞書は、言葉の海を渡るための舟のようなもの」みたいなことが、「舟を編む」では描かれています。
この時期に、2つの再放送を見ながら、”文字”・”ことば”について、意図的なこともがあるのだろうか?
勝手に想像してしまいます。
ひるがえって、現在の自分たちの世界では、AIを使うことも出てきました。
まだまだ、自動でなんでもしてくれるようなものでもなく、プロンプトと呼ばれる指示を一般的には文章で与えて、結果を得るという対話スタイルで使っています。
まさに、”ことば”を紡いでAIに自分の意図を伝えることから始まります。
AIは身体を持ちませんが、「深呼吸して」とかを付けると、応答の精度があるとかいう研究者もいます。
本当なのか?とも思ってしまいますが、衆議院内閣委員会のAI推進法の参考人意見陳述でも出ていた話です。
「舟を編む」では、人の感覚の話で、手がしびれるときの感覚として、「電気が流れたときのような」という表現も、実際に電気が流れた経験もないのに、その感覚を想像できます。
人の感覚の記憶も、思考も”ことば”なしには存在しない、さらに意識も”ことば”で考えている?
そう考えると、人でも、AIでも、実際にその経験がなくても、その意図や意味を想像できる共通認識を育むテレパシーのようなものかもしれません。
”ことば”とは不思議なものです。
