「独り言」:舟を編む 原作、映画、ドラマ~人の感じ方
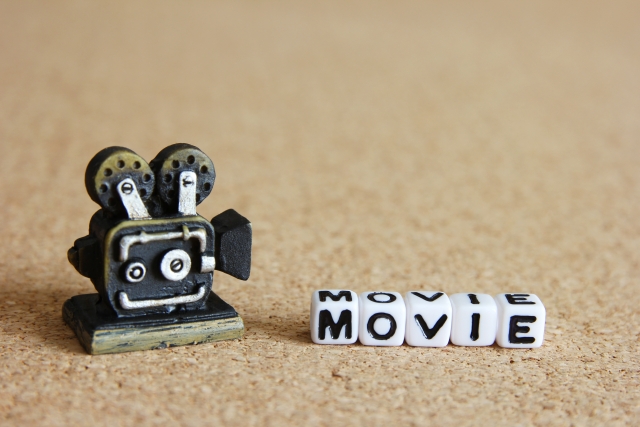
NHK BSで「舟を編む~私、辞書作ります。」で放送されたものを見ました。
自然言語関係の仕事を長年されていきた友人から、紹介されて見始めたように思います。
辞書を作る人の話ということで、最初はそれほどでもなかったのですが、言葉って何か素敵な感覚が次第に芽生えてきたように思います。
評判が良かったのでしょう。今度は、NHK総合のドラマ10での放送が始まりました。
そんな夏日に、たなたま、Amazon Primeを開いたら、”舟を編む”の映画がリストのTOPに。
最初は、NHKドラマかと思いページを開いてみました。
それは、映画でした。
しかも、2013年公開で、石井裕也 監督で、出演者は、松田龍平、宮崎あおい、オダギリジョー、黒木華…
NHKドラマと映画は、視点全然違うというか、時間軸が違うのです。
まあ、原作そのままでドラマになるわけでもなく、脚本家の視点がはいったりします。当然ですね。
こうなると、原作も読んでみたくなります。
原作からインスピレーションを受けて、映画ができたり、ドラマができたり。
二次創作物として、立派な作品なのです。
以前、角川が、小説と映画/TVのメディアミックスで一世を風靡した時代がありました。
「読んでから見るか、見てから読むか」
記憶は確かではないですが、本と映画は、それほど視点が違ったようには思えませんでした。
映画とドラマでは、ターゲットも違うし、時代も違うのですが、そういう違いを超えて、さらに原作のどこから、そういうインスピレーションを映像にするのでしょうか?
もし、AIに原作を入力すると、どんな映像になるのでしょうか?
脚本家や監督が、演者に指示を出し、演者は自分の表現として演じること。
AIに映像を作らせるために、同一の思考モデルで創り出される作品は、多くの人がかかわって作る作品。
これには、何か大きな違いがあるような感覚を覚えます。
原作は、一人の作者の思考で作られるものですが、映像作品になるときに、係る多くの人の異なる経験の影響を受けて意味出されるものだと思っています。
この記事は、映画「舟を編む」を見ながら書いています。
最後にもう一つ、「チコきゃんに叱られる」でみた話ですが、映像に音を加えると、映像を自分事として感じるような特性があるそうです。
映像作品は、出来た後も、見ている本人の過去の経験とも合わさって、感じるということ。
これも、映像作品の深みを増してくれるということなのだと、自分で納得しています。
この夏に、読んでみたい本が一つできました。
舟を編む (光文社文庫 み 24-2) 著:三浦しをん
